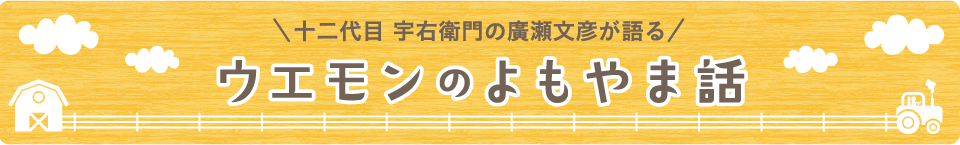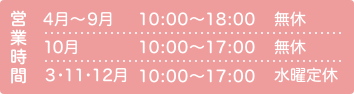阪大病院NOW
昨日帯広を発ち、今日は阪大受診。
太陽の塔とも1ヶ月ぶり。
脇を通って...
病院前
一年ぶりに宮川先生の診察室を訪ねると、治験アシスタントのS女史も在室。
そのS女史、開口一番「廣瀬さん、お痩せになった⁉️」と聞いて来る。
一年前から見ると2~3kgと僅かだが減ってはいるが、目に見えてと言うほどでは無い。
目の錯覚か⁈
そう言えば、1ヶ月前の有馬温泉に集まった酪農家仲間からも言われたなぁ!
阪大病院での検査結果も頗る良いとのお墨付きを頂いた。体重過多を除いては......
優先順位
今朝の道新。
ほぼ毎日紙面に、詐欺のニュースが載っているが、今日は24面のほぼ40%を占めている。
見出し順に
「金塊・現金 計1.22億円被害」ー札幌市西区50代男性
「投資勧誘1.16億円」ー札幌市手稲区の40代男性
「警官名乗る電話 2,500万円」ー小樽市70代女性
「交流サイトを通じて投資名目で2,150万円」ー札幌市白石区50代女性
「警官名乗る男に685万円」ーオホーツク紋別40代女性
「交流サイトを通じて投資名目で395万円」ー厚岸50代女性
「交流サイトを通じて架空の副業に仮想通貨で155万円」ー函館市40代女性
金額順で億の被害、千万単位、百万単位で見出しの大きさも小さくなっている。
こんな事で⁉️と思われる色々な手口の詐欺で騙し取られているようだけど、
良く考えて見ると、無い袖を振るい様がない我が家は心配無し。
地震
8日深夜、午後11時過ぎ熟睡中ドシン、グラグラで文字通り揺り起こされた。
寝室には転倒する物がないものの、体を起こしベッドのへりに座っていると、しばらくユラユラと横揺れが続く。
思いの外長く感じた揺れがようやく収まり、高齢の両親の部屋に行くと「大っきな地震だったな」と布団を半分めくって顔を出している。
この部屋も異常無し。
居間に行き、真っ暗な窓外には長男が車を出して牛舎の方に向かって行くのが見えた。
数分後、車のライトがパーラー兼事務所の前に戻ってきた所を見計らって、電話をしてみる。
長男は「牛舎の方は、立ち上がっている牛が普段より多いようだけど、落ち着いているよ。」との返事。
牛舎の方も一安心。
さてさて、震源や震度、はたまた他所の被害は?とテレビを点ける。
北海道、東北地方の太平洋岸は3mの津波警報。
日高の浦河の町に一人住まいで脚の悪い叔母(母親の妹で90才)の所は避難勧告が出ているかも知れないが、如何ともしがたく、
両親と家内とで、まんじりともせずに津波の第一波到達時刻までテレビに釘付け。
「こんな時に十勝から浦河の叔母さんに電話する訳にも行かないよな」などと話しながら、刻々入る地震情報に一喜一憂。
思いの外潮位は上がらず、ホットして眠りに就く。

十勝は地震の多い所。
30余年前の地震では、100頭近くの牛達が音と揺れに驚いて柵を壊して雪の中を暴走した事もあった。
先ずは一安心。
土砂搬出4日目
1日の作業量は3.5~4T✖️20台
2日目

木の下も構わず土砂を掘り取り

木を倒し搬出

4日目

4日で70〜80t運んだか⁉︎
まだまだ減らない「宝の山」だ。
モグラの気持ち
昔々、ノイエルと言う建設業を営む会社があった。
我が家でも1991年のミルキングパーラーの設計を始め、1995年に住宅。
1999年にウエモンズハート。
その後もフリーストール牛舎。そして堆肥舎などなど本当にお世話になった。
手抜きは全く無く、誠心誠意を尽くした施工をする為、十勝管内でも多数の物件を手掛けている。
扨、建物を構築するには基礎工事から始まるが、その際大量の土砂が出る為、我が家の敷地内に堆積して置いた。
その土砂が今、整地用として重宝している。
その山の斜面には数十本の雑木が生えているが、構わず水平に土砂を運び出して行くと......

根が剥き出しになる......

後にも先にも2度と経験できないと思って根の下から世間を覗いて見る......

モグラやミミズの世界観か?
奴らは眼が見えないけど......
イヤイヤ、熟考してみるに、自分自身遠からず住まうであろう黄泉の国からの眺めであろうか⁉️