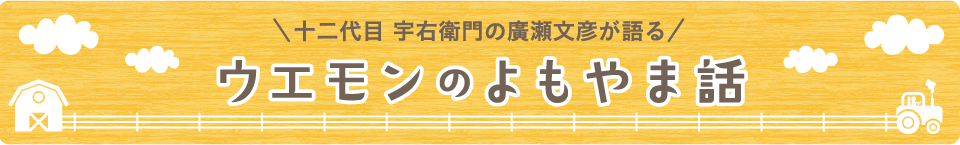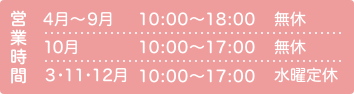食は命の親玉
今朝の業界紙一面。
論点。高知大学客員教授小田切徳美氏が「コメ問題と農村生活」の問題点について論じている。
「分断を架橋する関係人口」と、大見出しにあり、目を引く。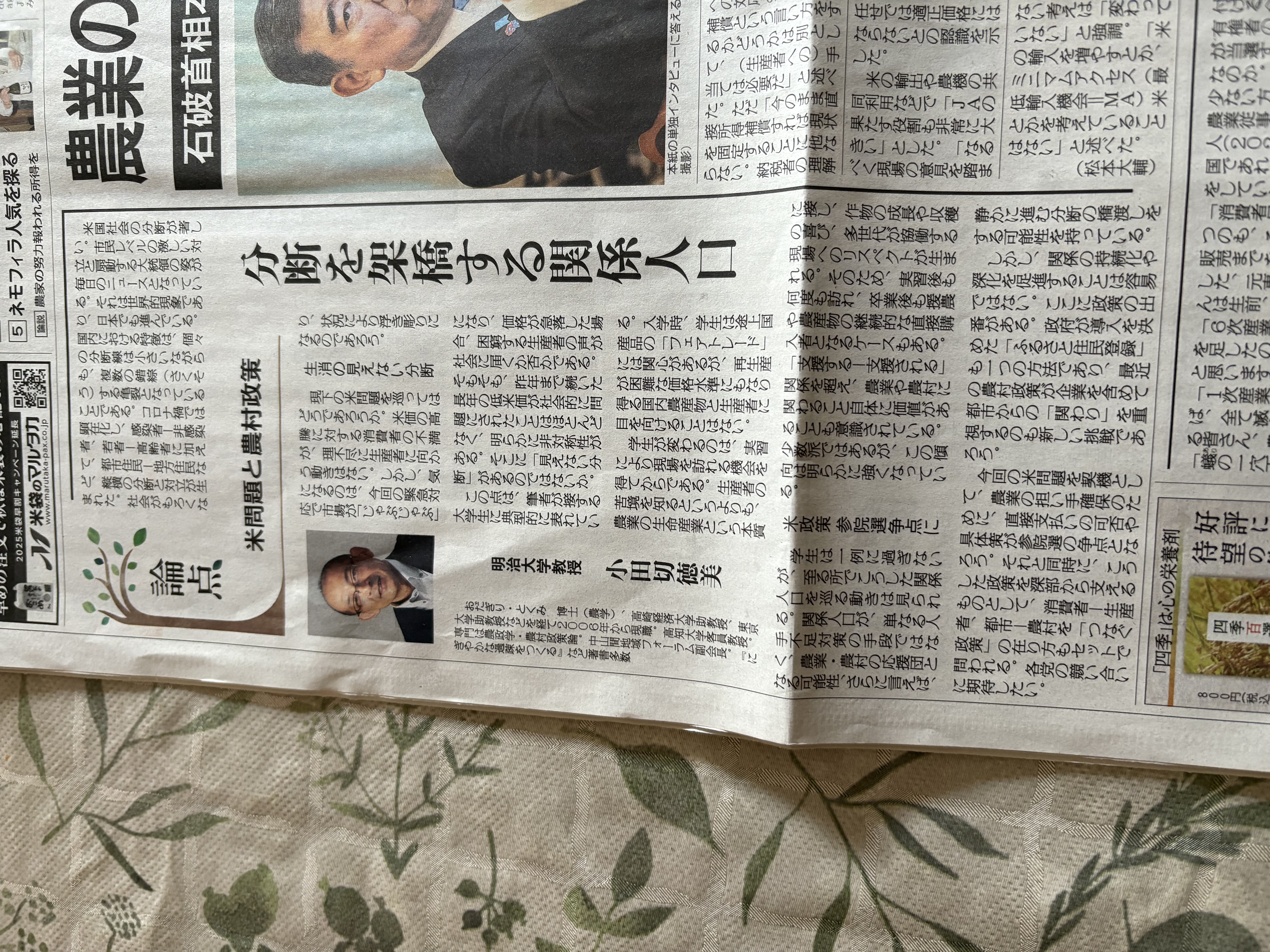
自分自身、遥か昔(自分の人生の中なのでたかだか35年程前だが)、「少数民族」となりつつ有る農家自身が、生産現場を開放して、食糧ができるまでを消費者に「伝えなきゃ」、食糧の価値は伝わらない。
つまり、作物の種を播いた後、灌水、除草、追肥などの農作業と同じで、消費者の口に食糧が届くまでを生活者に伝える事も
農家自身の「21世紀の農作業」であると自認し活動して来た。
この動きは、我が酪農業界では1999年、「酪農教育ファーム」として結実し、会員牧場には、年間100万人弱の学校や生活者が訪れている。
私自身としては35年、組織としても26年、関係人口作りに貢献してきているのだ。
小田切教授はこの事を、トランプ政治や小泉コメ大臣の劇場政治に見られる社会の分断、非対称性から読み解き、消費者理解が必要と解説している。
彼の下に集まる学生達は、入学時、途上国産の「フェアートレード」には関心があるが、
再生産が困難な価格水準にもなり得る国内農産物と生産者に目を向ける事はない。
学生が変わるのは、実習により現場を訪れるようになってからである。
農業の生命産業と言う本質に接し、作物の成長や収穫の喜び、多世代が協働する現場へのリスペクトが生まれる。
こう言う学生達は、農業、農村の応援団となりは可能性、さらに言えば、静かに進む分断の橋渡しをする可能性をもっている、と述べている。
つまり、農村自から、関係人口を増やすための能動的な活動が必要であると、説いている。
変わって、同紙面下段の「四季」には6次産業とは1次、2次、3次産業を足したのか、掛けたのか、どちらか。」
正解は掛け算。「1次産業がゼロになれば、全て滅ぶ」だそうだ。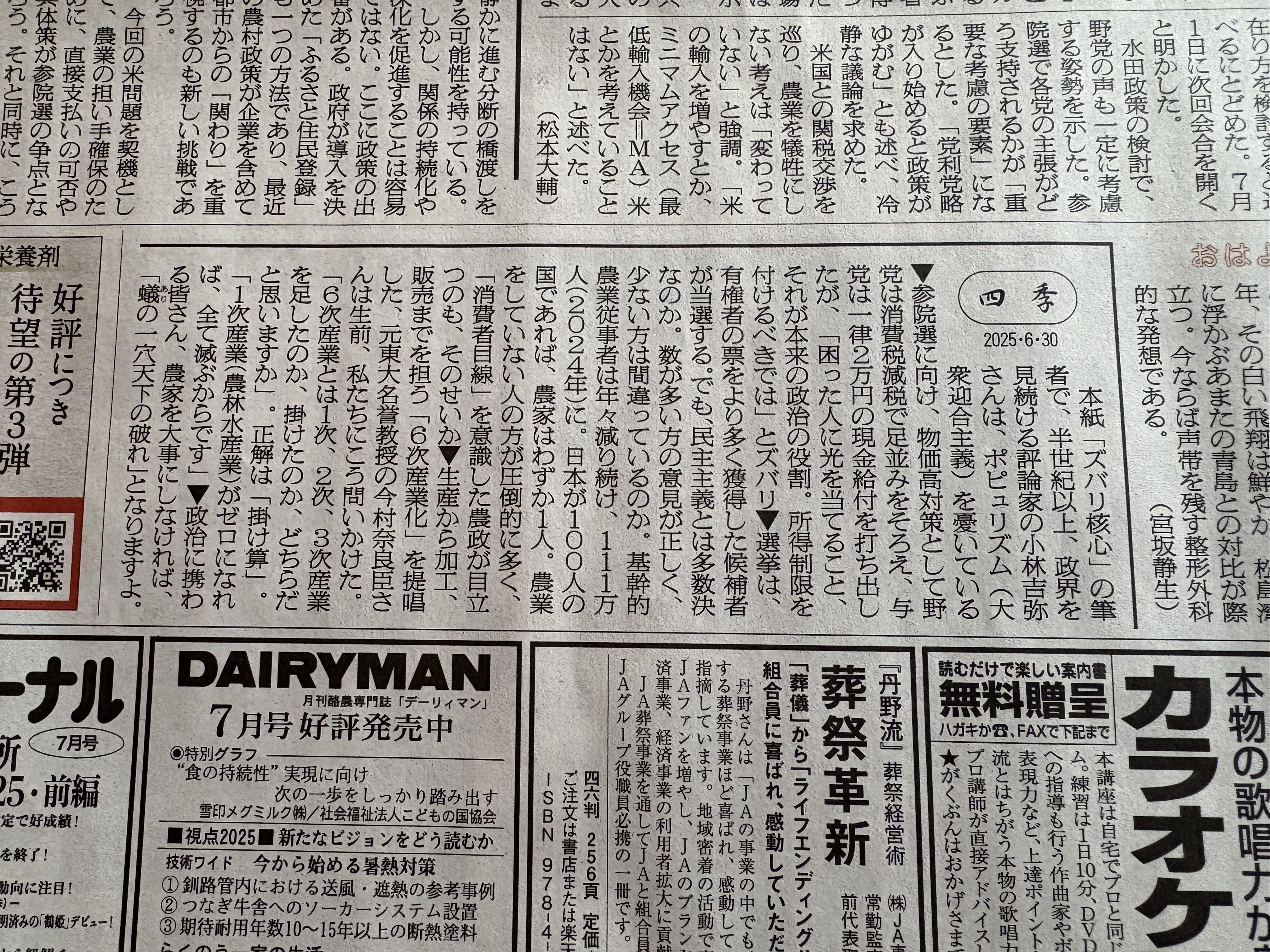
自分自身は足し算かと思っていた。1次➕2次➕3次