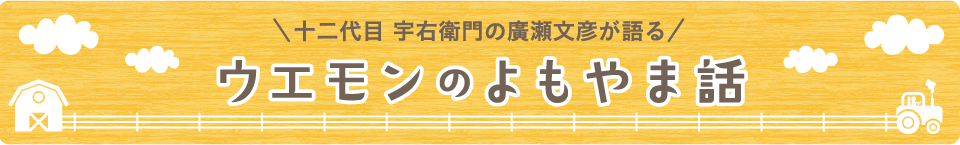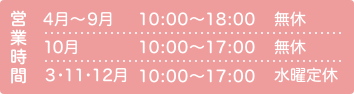だぁれだ
古い写真が出てきた。

脱穀したばかりの豆殻を馬車で運んでいる様子を写したもので、
この小さな御者は67年程前のオレです。
「エッ?猫の手も借りたいくらい忙しく、4〜5才の子供も農作業に駆り出されたのか?」って?
「まさか!子どもの仕事は親の邪魔をしない事さ!」
定期受診
2/20.朝から札医大の小山雅之先生の診察を受ける為、
19日午前10時半頃我が家を出発する。
冬の峠越えはきついので、バスでの札幌往復を考えていたけど、休暇を取って帰省中の次男と、牧場と店の税務処理があらかた片付き嫁の実家に移動する三男か同行することになり、
自家用車で出発する。移動日は、峠も含め札幌まで殆ど夏道。
お陰様で肩も凝らずに走破。高速を降りた札幌屯田あたりで遅めの昼食を4人で摂り、
三男の嫁の実家に向かう。
実家では茶菓のもてなしをうけ、更には三男の長女(孫)の3才の誕生日祝いも我々の訪問に合わせて開いてくれた。
訪れる度、姑さん達の心遣いが嬉しい。
20日の札幌は昨日と打って変わって降雪がすごい。それにもめげず本来の目的の札医大、午後は家内が大野記念病院受診と病院のハシゴ。
札医大の小山先生には、レントゲン検査の結果、心臓の肥大が出てきていると指摘された。
先月アミオダロンと言う薬を半分に減らした事が影響しているかも知れないという事で、
元の量に戻してもらった。bnpは18代で健常者並なんだが...
自覚症状としては喉が渇きを覚え飲水量が増えていたのと、短時日で体重が3kg程増加していた。
直前の16日には帯厚生で寺嶋先生のペースメーカー外来を受診したのだが、気になる不整脈が少し増えていると
診断されていて、矢張り拡張型心筋症は治ってはいなくて、日頃の行動を見直さなければならないと少し
気の引き締まる受診であった。
そして翌21日は、先月13日に87才で亡くなった実習先の親方の遺影に手を合わせに、千歳にある牧場に寄らせて貰った。
実習は昭和45年の一年間でもう半世紀以上も昔の事。
慰めになったかどうか分からないが、奥さんと、親方との思い出話をひとしきりさせてもらった。
その後、都会志向で高卒後20年以上首都圏暮らしの次男に、ふるさと北海道の広さを実感してもらうと道東自動車道は走らず、千歳から安平、厚真、平取、日高、日勝峠を経由して帯広に到着。
愛車の汚れが余りにもひどい為、JAのスタンドで洗車そして注油して午後5時過ぎ家に帰り着く。
到着時のメーターは
差し引き、札幌往復448km走ったが、次男は日勝峠から見た広大な十勝平野から、
農業王国十勝の豊かさを実感していたようだ。
どうだ、十勝、スゴイだろう!
伊豆松崎町長
明治14年、静岡県の伊豆半島に有る松崎町から、依田勉三率いる晩成社の13戸の人々が
帯広開拓に着手し、こんにちの帯広があると言う事で姉妹都市として提携交流している。
その松崎町の町長さんが、今日午前我が家に表敬訪問して頂いた。

来場記念に写真を撮らせて頂きました。
写真左から町会議員兼桑の葉で町おこし6次産業化推進副代表兼同町帰一寺住職田中道源さん。
私を挟んだ右隣りが松崎町町長の深沢準弥氏、そして随行員。
コロナ禍で途絶えていた両市町の青少年交流を再開させる事など、何点かの用向きを話し合わせていただいた。
松崎町は伊豆半島先端部に位置し、平らな所も殆ど無く人口減少に歯止めがかからない。
そんな中松崎町の先達が、国の大元は農業に有りと大志を抱いて北海道開拓に人生をかけた。
そこが現在の帯広で、北海道内でも有数の農業地帯に発展している帯広市との連携した町おこしに力を入れている。
広瀬牧場ウエモンズハートも農業者として、微力ながらお手伝いは喜んでお受けする旨、お話しさせて頂いた。
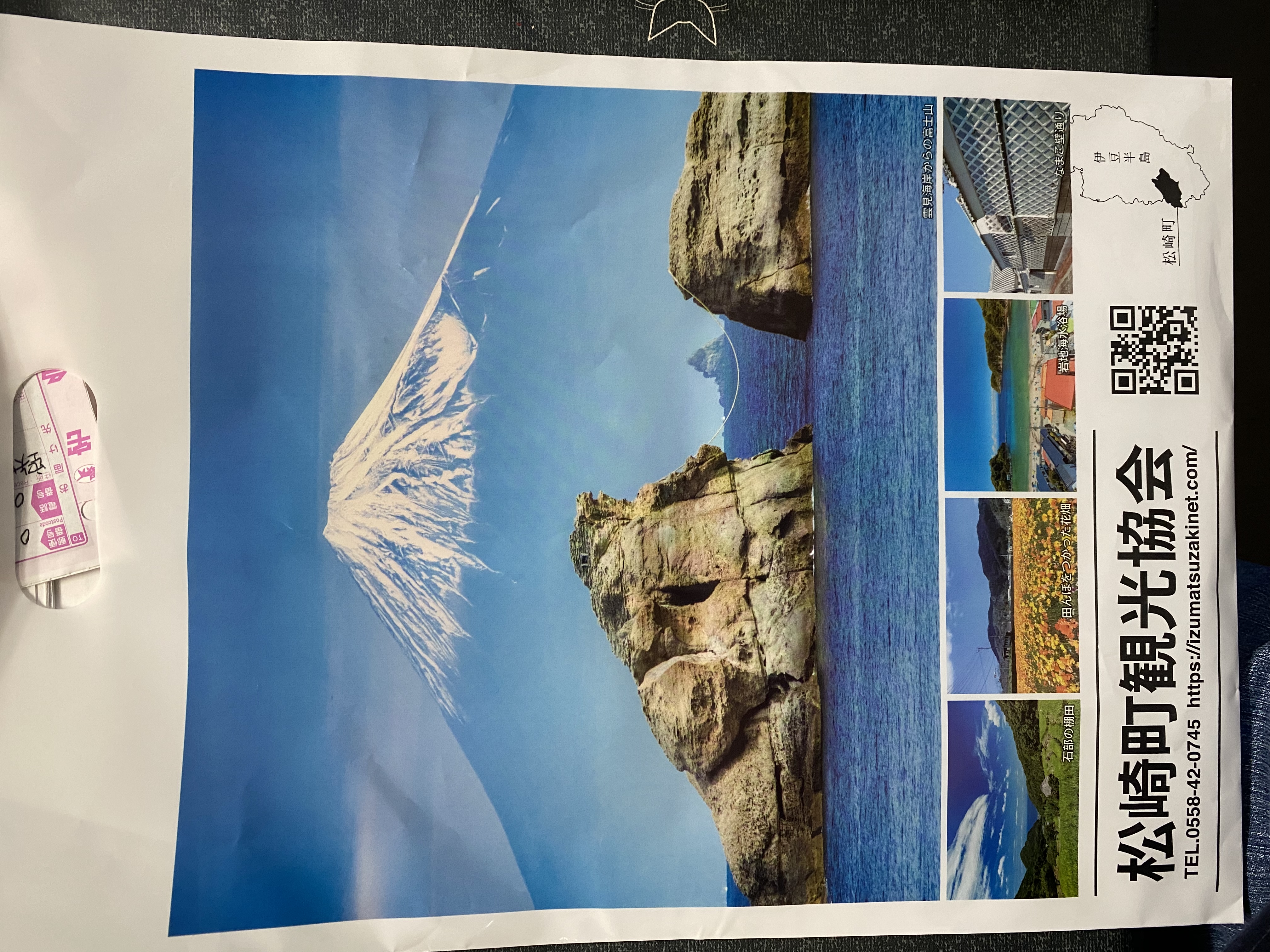

同町の観光協会の袋に町の特産物を沢山詰めた物を土産にいただいた。
ありがとうございます。
話しの最後には広瀬牧場は芸能界に関わりが深く、帯農生の学生生活をモデルにした『銀の匙』実写版では広瀬アリスと中島健人が広瀬牧場で酪農実習と撮影に使って頂いた事。
またNHKの朝ドラ『なっぞら』の撮影ではアリスの妹の広瀬すずと、姉妹共に深く関わらせて頂いた話しをすると、
アリス、すず姉妹も静岡産だという事で大盛り上がり!
牧場の新撰組
2月も中旬となると日中はあったかくなったなぁ、ニャローども!
さあ、ネズミはワルサをしていないか、パトロールだ!
何てったってロシアとウクライナの戦さが始まって以来、過去に経験した事が無いくらい牛のエサが値上がりひどく、うちの親方は困っているんだ。
野ネズミの奴ら、そんな事お構いなしにバンカーのデントコーンサイレージを盗み食いしている。
しかもそのネズミ達は長期保存のため被覆しているビニールを好き勝手に食い破って食べているんだ。
そのエサは乳酸菌で嫌気性発酵して保存している為、外気に触れると腐ってしまう。
と言う事で、困っている親方を助ける為、いざ出動!
捕獲したら、各自戦利品として喰ってしまっていいぞ!
ちょっと、待ってくれ〜、オレも手伝う〜
今日のことば
今日は「聖バレンタインデー」だ。
チョコレートが頂けるか、頂けないか。はたまた義理か本命か。
皆さん大いに悩んで下さい。
扨、諺カレンダーには「恋に師匠なし」とある。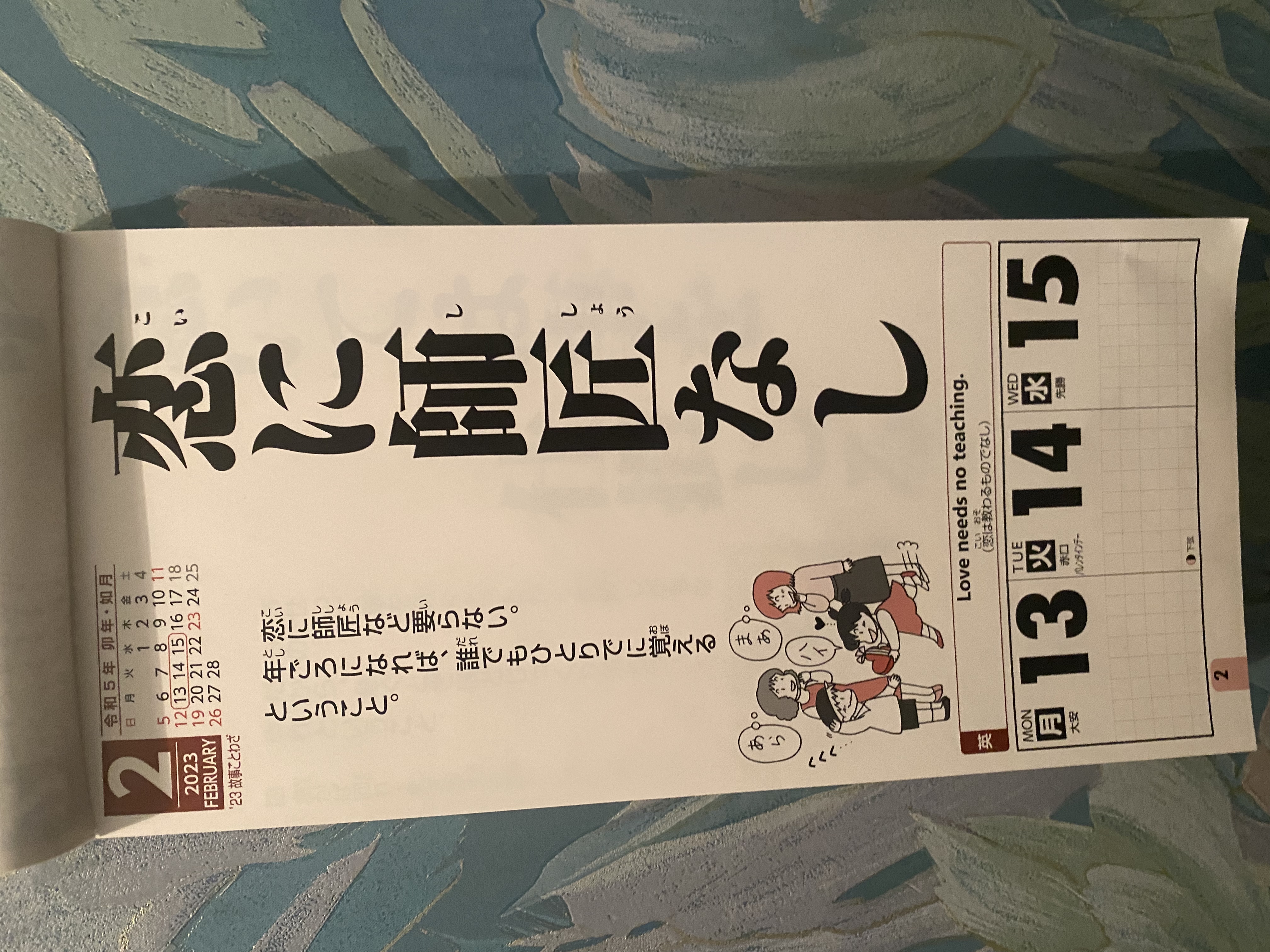
この言葉を見て、自分が過去関わっていた、ある団体での事を思い出した。
その団体では、農村の花嫁対策にも力を入れていた。
その対策事業計画には、「女性との会話の仕方(方法)」についての研修会と言うものが有ったが、
いつも違和感が有った。
これは未婚の農村青年を対象としているが、勿論異性に興味の無い人には強要されるものではない。
それを前提とすると、人間いや全ての生き物は、年頃になれば何となく異性に興味が湧き、そして気を引こうと言う行動が顕著になってくる。
鳥の世界では、♂の方が派手な羽を持ち、季節になるとその羽を見せびらかす様に、♀の周りで必死にアピールしている。
野生動物の世界では♀の周りで気長に♂は自己アピールに努めている。
一生懸命にアピールしている最中、強い♂やカッコいい♂がライバルとして現れればその♂は
時として命を賭して戦うのだ。
そして自分は「青春」とはそう言うものだと理解し生きて来たし、そう行動した。
野生の世界では、♀にアピール出来る踊り方だとか、振り向いてくれない♀に理解を得られるまで短気を起こさず
気長に自己アピールを続けなさい。彼女はこれから貴方と一生添い遂げられるかはたまた強い遺伝子を子供に残せるか、じっと吟味しているのよ、
などと言った研修会は開かれていない筈だ⁉︎
男性は好意を持った女性の「個性」に、どれだけ寄り添えるのかアピールする事が大事なのでは。
その諺カレンダーの下段に英語で
「Love needs no teaching(恋は教わるものでなし)」とある。