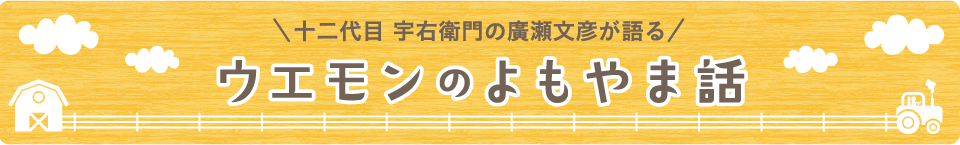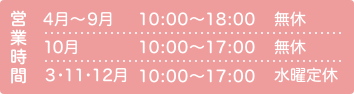春を拾う2
 何だこれ?何が悲しくて、枯れ枝の写真をアップしているの・・・?と言いたい気持ちは良くわかります。が、良~く枝先を見てください。白い物がチラホラ・・
何だこれ?何が悲しくて、枯れ枝の写真をアップしているの・・・?と言いたい気持ちは良くわかります。が、良~く枝先を見てください。白い物がチラホラ・・
もう一枚アップしてみます。
 オォ、この写真なら目に付くと思います(なんも変わらん、なんて切り捨てないで下さい)。左の大木から右上のほうに延びている枝先を見てください!
オォ、この写真なら目に付くと思います(なんも変わらん、なんて切り捨てないで下さい)。左の大木から右上のほうに延びている枝先を見てください!
そうです北海道の早春を象徴する辛夷の花です。昨日とは打って変わって寒さが身に染む今日、けなげにも辛夷の花が咲き始めました。嵐雪の句「梅一輪 一輪ほどの暖かさ」ならぬ「辛夷一輪 一輪ほどの暖かさ」です。今は亡き叔父が中学生になった頃と言いますから昭和24~25年に近くの藪から掘って来て植えたものなので、樹齢75年位になりますか。
父は、辛夷の花の付き具合でその年々の畑の豊凶を占っています。その言を信じれば今年は花の蕾が少ないような・・・・
今度は満開の写真もアップします。
大日本帝国陸軍遺産Ⅰ
住所で言うと帯広市西22条南5丁目。と言ってもピンと来る人は殆どゼロだと思いますが・・今を去る事75年前の第二次世界大戦が始まる前後、日本陸軍航空隊熊部隊の飛行場が(現在の自衛隊第5旅団のある位置)敵機に空襲されることを懸念して、弾薬等を分散保管していたそうです。
しかも空から見えにくい場所に保管したそうです。その現場に通じる道路が次の写真です。


 70年近くを経て道路であった所にもご覧の通り大きな木が生い茂っていますが、今でも落ち葉を掻き分けてみると砂利を敷いた立派な(?)道路が確認できます。帯広川の河岸段丘になっているこの裾野に沿って道路を取り付け、奥まった所の崖に横穴を掘り武器、弾薬を保管していたそうです。その横穴は敗戦時爆破され裾野がえぐれたかんじで窪んでいました。高台は畑、下台は水田ですが、その狭間の傾斜地は自然の林の儘で空からは見えにくいその部分に道路を付けたようです。
70年近くを経て道路であった所にもご覧の通り大きな木が生い茂っていますが、今でも落ち葉を掻き分けてみると砂利を敷いた立派な(?)道路が確認できます。帯広川の河岸段丘になっているこの裾野に沿って道路を取り付け、奥まった所の崖に横穴を掘り武器、弾薬を保管していたそうです。その横穴は敗戦時爆破され裾野がえぐれたかんじで窪んでいました。高台は畑、下台は水田ですが、その狭間の傾斜地は自然の林の儘で空からは見えにくいその部分に道路を付けたようです。
長い年月を経て木や笹に覆われて写真では分かりにくいんですが、画面の端から迫ってきている高台の裾野を削り道路を開削したものです。
日本が世界を相手に世界大戦を戦ったことすら知らない世代が増えてきている今、軍都帯広の軍事遺産を記憶にとどめてほしいと思います。
この場所は今は帯広市の所有する帯広の森として整備されていて、その中を縦横に散歩用やジョギングの為の道を取り付けています。22条5丁目の部分は今後整備する予定のようなので、その軍用道路を再生整備して利活用と保存をしてほしいものです。

 なんとも分かりにくいのですが・・・・
なんとも分かりにくいのですが・・・・
今度は遺産Ⅱとして掩体壕をアップしてみます。請う、ご期待を!
これ何て言うの?
昨日の朝、畑から湯気が立ち上っていました。
ウエモンズハートのスタッフが出勤途中に珍しい風景なのでスマホで撮って来たんですけど、これはどう言った現象なんですか?と質問を受けました。
スタッフも、男64歳百性歴44年、子供の頃の手伝いを含めると半世紀以上の百性経験者であるこの親父に聞けば疑問解決と思ったのでしょうか?なんの買い被り・・・!「昔から雨上がりの翌日、早朝から晴れて気温がグングン上昇する日によく立ち上る湯気なんですが・・、正式名称は知らず。今日は朝から畑に湯気が立ち上っていて温かくなりそうだね。農作業に精を出さなきゃ!!」なんていつも気合を入れられていました。
スタッフの期待に反してこの現象の正式な名称を知らず、Googleで(春先畑から湯気が立ち上る現象)と入力したら"地霧"と出ていました。出現条件は雨が前日に降ったり畑を耕起した翌日など畑の表面に充分な水分があって、尚且つ早朝から好天に恵まれると出るので百性の息子としては朝から追いまくられる恐怖の一日の始まりでした。これはどういう現象なの?何て考える暇もありませんでした・・(いやあ幾つになっても恨み節になってしまいます、私的には、万に一つの例外なく確実に一日中畑に拘束される"恐怖の霧"とでも表現できます)。ま、しかしこの年になって清濁併せ呑める様になってみると、長閑でうららかな春先の気持ちをふっくらと包んでくれる霧です。
重ねて言います。「恐怖の霧」ではなく「地霧」です。ハイ・・・
太一君
 友人を紹介します。今を去る事49年前蝦夷農、もとい帯農に一緒に入学した太一君です。もう65歳です。当時から何となく気が合う中で今はしょっちゅうメールのやり取りをしていますが、昨夜喜びのメールが飛び込んで来ました。英語の教師をしている下の娘さんから「今度の連休に結婚を決めた人を連れて行くので・・・」と電話があり、全く予想だにしない寝耳に水の話(嬉しい場合はそういう表現はしないのか?)で嬉しかった。姉娘もつい先月入籍したばかりで刺激されたのかな?でも全く気が付かなかった!」らしい。
友人を紹介します。今を去る事49年前蝦夷農、もとい帯農に一緒に入学した太一君です。もう65歳です。当時から何となく気が合う中で今はしょっちゅうメールのやり取りをしていますが、昨夜喜びのメールが飛び込んで来ました。英語の教師をしている下の娘さんから「今度の連休に結婚を決めた人を連れて行くので・・・」と電話があり、全く予想だにしない寝耳に水の話(嬉しい場合はそういう表現はしないのか?)で嬉しかった。姉娘もつい先月入籍したばかりで刺激されたのかな?でも全く気が付かなかった!」らしい。
今は高学歴からか晩婚化が進み30歳を過ぎないと結婚しない人が多くなったような気がします。私の親父(89歳)の時代は「二十歳ババア」と言ったらしい。我々の時代は「25歳くらいまでは結婚したいね・・」と言っていたっけ。すると今は30過ぎが当たり前か。私どもの次男坊も年には不足は全く無く、親としても心の準備も万端なんですが・・・
兎も角おめでとう。
干支
 JA信用部貯金課で貯金の謝礼に出している干支の貯金箱です。正確なことは忘れてしまいましたがもう40年ほど前からでしたかネ・・・
JA信用部貯金課で貯金の謝礼に出している干支の貯金箱です。正確なことは忘れてしまいましたがもう40年ほど前からでしたかネ・・・
先日妹の孫が小学校に入学したのでお祝いを届けに行って来ました。新一年生とその下の4歳の子は女児。末っ子は男児で1歳3ヶ月。母親とともに実家に来ていたので、皆で大騒ぎ。
妹の家では大画面のテレビの前に上のような12種揃った干支の貯金箱が並べてあります。見ていると1歳の子がその貯金箱をつかんでは放り投げて遊んでいました。「あ~あ、バラバラにしちゃったら、元に戻せないよ!」なんて言っていると、1年女児が「大丈夫だよ。え~と、これが子(ね)でしょ。次は丑(ウシ)でしょ。とら、う、たつ、・・・・・と並べるじゃありませんか。「じゃあミユメは何年?」「ミユメはトラ。おじいちゃんもおばあちゃんも、お父さんお母さん、妹も皆知っているよ!!」と言うじゃありませんか。
初めて孫の出来た我々夫婦もそれには触発され、あちこちに散らばっている十二支の貯金箱を探し出し、掻き集めてきて並べてみました。そして暇があれば「これはネズミさん」「これはウシさん」「これはトラさん・・・・・・・・」などと意味不明な言葉しか出ない孫と呪文のように唱える日課が始まりました。
夜は夜で曽祖父が唱えるお経さんもしっかりと聞き耳を立てて、聞いているのでそのうち口からひとりでに出るように成るかも。89歳の父曰く「これで彦の代までお経さんを上げて貰える」と、夜の御勤め読経にも一段と力が入っているような・・・・