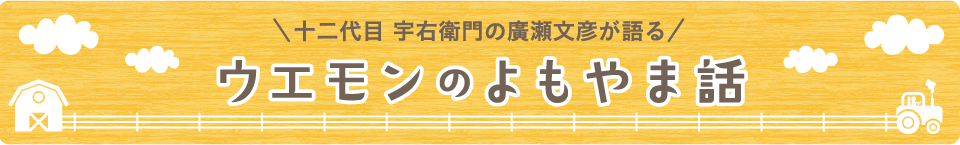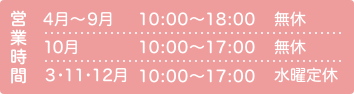始まった!!
蝦夷梅雨もようやく終わったようです。気温も昨日は前日比プラス10℃の24℃に、そして今日も晴れ、暖かい日になりました。この日を待つのに痺れを切らしていた息子が、喜び勇んで牧草の刈り取りを開始しました。
 どうです、この青空!!
どうです、この青空!!

本当に待ちに待った好天。牧草は窒素分が少なく甘くて美味しそうな黄緑色(窒素過多になると濃緑色になり多収穫にはなるんですが、草自体は苦味が増して牛も殆ど喰わなくなります)。その奥には濃緑色の木立によってより強調される空の蒼・・・いやあ、本当に百性やっていて良かったと思う瞬間です。

近くによると夏草特有の草いきれ・・・、自分の人生の中で最も記憶に残る匂いのひとつです。(他には?と言われれば田舎香水かな・・・)
明日は朝から切り込みのようです。いよいよです。
何日ぶり?
今朝は午前4時頃には太陽が久しぶりに顔を出していました。
本当に何日ぶり?
 庭の緑の日向と日陰のコントラストがなんとも言えず、気持ちがいい!!
庭の緑の日向と日陰のコントラストがなんとも言えず、気持ちがいい!!
 居間に迄日が差し、窓に部屋の中が映っていますが(なまくらせずに表に出て写せよ!!!)天気が良いのはやはり気持ちいい。
居間に迄日が差し、窓に部屋の中が映っていますが(なまくらせずに表に出て写せよ!!!)天気が良いのはやはり気持ちいい。
けどタンポポが気になるな・・・・・
この花なんて言うの?
昨日は少し晴れ間が・・・・いよいよか!?と、期待させるような天候でしたが、またしても今日も雨。しかも結構強い降り・・・
スタッフが牧場横の道路沿いに植えられている花が満開・・・!と言うことで写真を撮ってきてくれました。
この道路は市街地の人たちの運動がてらの散歩たなっていて、レンギョウに始まりサクラ、ライラック、ハナモモ、そしてこの花・・・・に皆足を止めてくれます。
そしてまた、「例によってこの花はなんという花なんですか?」(オレは花屋じゃなくて牛屋だぞ・・)と心の中で毒付きながら、「ハテハテ名前はねェ、ちょっと・・・調べておきます。ハイ!」
やはりネットで、ポン!日本原産スイカズラ科のウエイゲラ・モーリンルージュだそうです。日本原産と言いつつ、何故モーリンなんとかなんだ?
痛い出費
先日、腕時計を車で轢いてしまった話をアップしました。
 見るも無残な姿でしたが時計本体は何事にも動せず"チッ、チッ、チッ・・・・・・"そこで修理に出しておいたのでしたが、このほど出来上がりました。
見るも無残な姿でしたが時計本体は何事にも動せず"チッ、チッ、チッ・・・・・・"そこで修理に出しておいたのでしたが、このほど出来上がりました。
 〆て7776円の予算外の出費。
〆て7776円の予算外の出費。
しかし今は私の腕で、"今度からはもう少し大事にしてね!"言いながらも幸せそうに再び時を刻んでいるスカーゲンなのです。
38回目
明日6月24日は店長と私の38回目の結婚記念日です。昭和53年もこの日まで天候不順で牧草の収穫が全く手付かずの状態でした。そして24日蒸し暑い一日でしたが無事結婚式終了。翌日から車で東北地方へ新婚旅行に出発・・・・そして6月30日帰宅。するとどうでしょう我々は新婚と言うことでノー天気にも遊んでいる間、天候にも恵まれ、牧草の大半がコンパクトベーラーで収穫され畑に沢山積まさっているじゃ有りませんか・・・!残された者の事も考えず、そんな申し訳ない新婚旅行をしてきたのでした。
それは置いといて、今年も天候不順で牧草の収穫も手付かず!家族のイライラもピークに(自分だけか?!)・・・。店長も終日予定は入れていないということで、急遽思い立って釧路まで海鮮を仕入れに行って来ました。
 釧路と言えば和商市場です。まず品定めをする前に・・
釧路と言えば和商市場です。まず品定めをする前に・・
 和商市場と言えば、勝手丼かカニでしょ!!と言うことで花咲ガニを一パイでお腹も一杯!!
和商市場と言えば、勝手丼かカニでしょ!!と言うことで花咲ガニを一パイでお腹も一杯!!
ニシン,サンマ、時知らず、ホッケ、カレイ、塩辛、松前漬け、サンマ丼(一人前ずつ袋に入って温めればすぐ食べられる)の素、カニコロッケ等‥手当たり次第に購入!
そして今夜のメインイベントのために手巻き鮨の用意!大トロ、中トロ、シメサバ、うに、とびっこ、ホタテ、海老、カニのむき身等も用意!
今回は道東自動車道で帯広~阿寒まで行きその後大楽毛を通って釧路駅横の和商市場へ直行。
そして店長の高校時代の思い出(どんなドラマが有ったのやら・・・)の喫茶店兼レストラン「泉屋」へ・・
 カニでお腹一杯のはずがここでまた卑しくも名物スパゲッティも頂く。今でも1.5食程の大盛りなのに当時は更に大盛りを頼んだのよ・・だって!あれから50年、そんなに食べられないよ!と言いながら完食。
カニでお腹一杯のはずがここでまた卑しくも名物スパゲッティも頂く。今でも1.5食程の大盛りなのに当時は更に大盛りを頼んだのよ・・だって!あれから50年、そんなに食べられないよ!と言いながら完食。
そして同じコースで帰宅。往復とも店長の運転でした。
すっかり運転に自信をつけた店長曰く「釧路って2時間かからないで行けるのね!これから月に一度くらいのペースでお義母さんやお嫁さんと買い物に来れるわ・・・」だって!
くわばら!、くわばら!