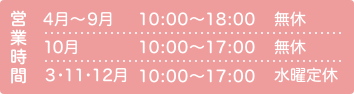昭和38年2月2日
オレが小学校五年生だったこの日の朝。
「にいちゃん起きて、おきて。大変だ。とっしょりばーちゃん死んだみたいだよ」と、同じ部屋で寝ていたはずの妹の絹子がオレを揺り動かしている。
熟睡を起こされたオレは、寝ぼけ眼で「まさか⁈」と(多分不機嫌そうに)目を擦った。
「だって、ばーちゃんの部屋にお医者さんも来てるよ」と絹子。
夕べの夕食のカレーライスを「美味しいなぁ」と言ってキレイに食べていたのに、俄かには信じられなかった。
しかし、ただ事では無さそうな顔で「ほんとだってば」と言い募るばかり。
ようやくの事布団から出て階段を降りて見ると、ただ事では無さそうな雰囲気の中隠居部屋の前に行くと、
はつばーちゃんの長男で祖父の種治と、白衣を着て首に聴診器を掛けた緑ヶ丘の佐藤先生がはつばーちゃんの枕元で
向かい合う様にして何やら話し込んでいる。
布団の足元から見えるはつばーちゃんの顔はスヤスヤと眠っている様だった。
はつばーちゃんの思い出
4才の頃(昭和31年)のオレとはつばーちゃん

同じ年の夏。庭にて

米寿のお祝いを前に、記念写真を撮る

明治9年生まれのはつばーちゃんはいつも着物姿だった。
毎朝鏡台の前で、着物の衿に白いハンカチや手拭いを挟み、左手に手鏡、右手に柘植の櫛で髪をとき、集めた髪を後ろに纏めて整えていた。
身綺麗なばあちゃんだった。
そのばあちゃんが突然亡くなった。
それがタイトルに有る日時で、今日で63回目の命日だ。